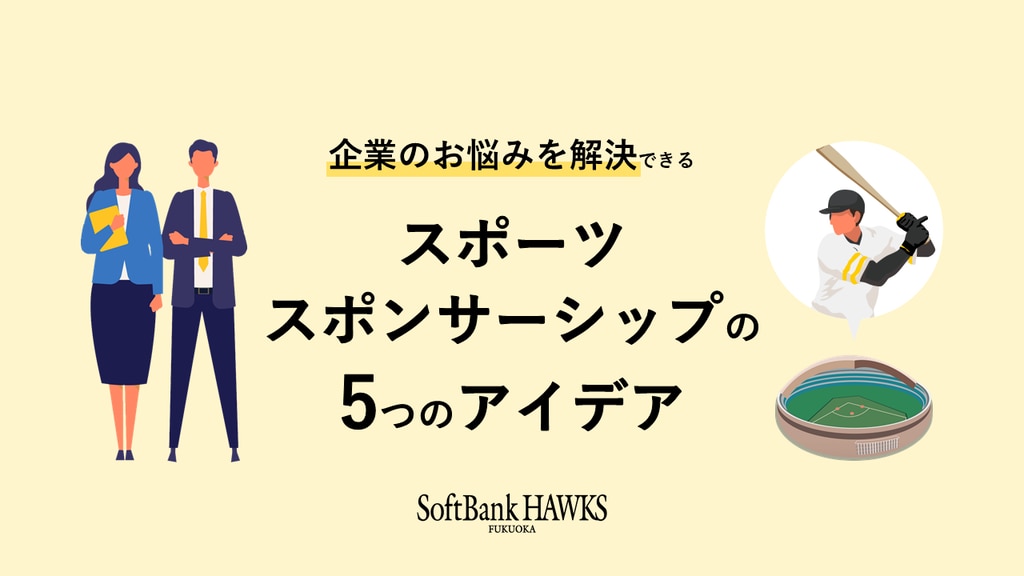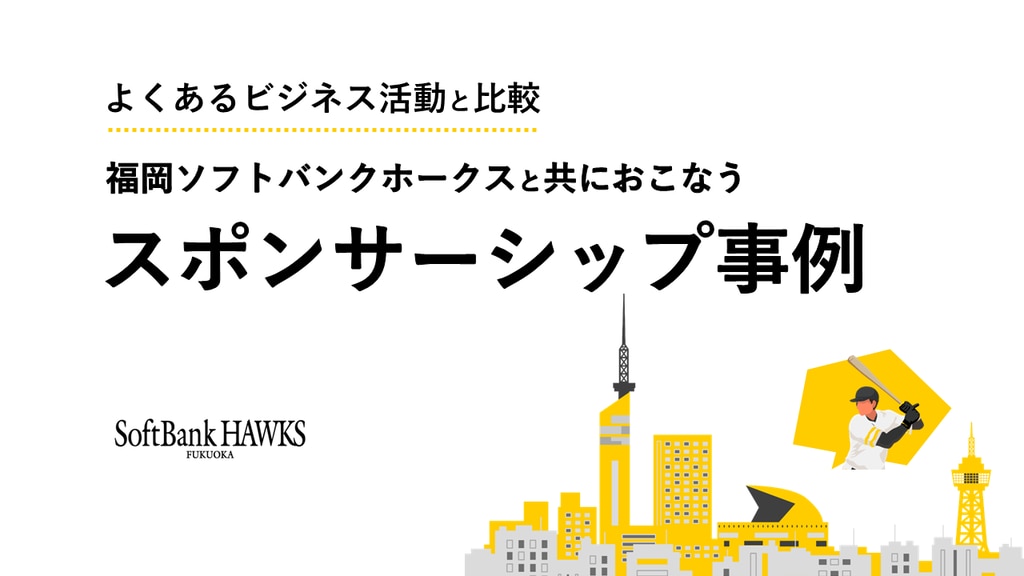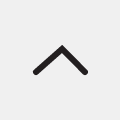共催と協賛の違いとは?パートナーシップの形を徹底解説

イベントの開催に向けて、心強い味方となるのが「共催」や「協賛」といった形で協力してくれるパートナーの存在です。「共催」と「協賛」どちらもイベントをサポートするイメージがありますが、その役割やメリット、そして責任の範囲は大きく異なります。
本記事では、イベントを成功に導く上で不可欠な共催と協賛の違いについて、具体的な事例を交えながら徹底的に解説します。
>おすすめの関連記事はこちら
・協賛企業とは?定義や協賛形態を徹底解説
・イベント協賛とは?プロ野球を活用した企業のブランド認知と福利厚生
目次[非表示]
- 1.共催と協賛の違い
- 1.1.共催とは ?
- 1.2.協賛とは?
- 1.3.共催と協賛の違いを比較表で整理
- 2.共催と協賛のメリット
- 3.福岡ソフトバンクホークスへの協賛事例
- 3.1.協賛事例①:ホークスカップ
- 3.2.協賛事例②:イベント試合への協賛
- 4.まとめ
共催と協賛の違い
共催とは ?
共催とは、複数の組織が対等な立場で協力し、ひとつのイベントを企画・運営することを指します。文字通り「共に主催する」というニュアンスが強く、イベントの成功に向けて、企画段階から運営、そしてその成果までを分かち合うパートナーシップの形です。主な特長は以下の通りです。
- 共催の定義と特徴
共催の最も重要な特徴は、責任と権限を共有する点にあります。イベントの名称に両者の名前が併記されることが多く、「〇〇社・△△社 共催」といった形で表記されます。 - 共同責任・共同権限
イベントの企画立案、予算策定、広報宣伝、実施運営、そして結果に対する責任と権限を、共催者間で分担し、共有します。 - リスクとリターンの共有
イベントが成功すれば、その成果(集客、収益、ブランドイメージ向上など)は共催者間で共有されます。一方で、万が一失敗した場合のリスク(損失、クレーム対応など)も同様に共有することになります。 - 相互の強み活用
各組織が持つノウハウ、人材、ネットワーク、資金などのリソースを相互に持ち寄り、より大規模で質の高いイベントを実現できる可能性が高まります。 - 対等な関係性
基本的には、共催者間は対等な関係にあります。どちらか一方が主導権を握るというよりは、協議を通じて意思決定を行い、共にイベントを推進していきます。
協賛とは?
協賛とは、イベントの趣旨に賛同し、主に資金や物品、サービスの提供を通じてイベントを支援することを指します。
共催のように直接的な企画・運営には関与せず、主催者側が主体となってイベントを進行します。協賛の最も大きな特徴は、金銭的または物質的な支援を行う点にあります。
協賛者は、その支援に対する見返りとして、広告効果や企業イメージ向上などのPR効果を期待します。

主な特長は以下の通りです。
- 主催者が主体
イベントの企画、運営、責任はすべて主催者側が負います。協賛者は、あくまでイベントを「支援する」立場であり、直接的な運営には関与しません。 - 支援の種類
主に協賛金(現金)の提供が中心ですが、物品の提供(景品、備品など)、サービスの提供(会場提供、輸送協力など)も含まれます。 - PR効果
協賛者は、自社のブランド名やロゴの掲出、イベント会場でのプロモーション、参加者へのサンプリングなどを通じて、自社の認知度向上やイメージアップを図ることを目的とします。
共催と協賛の違いを比較表で整理
項目 | 【共催】 | 【協賛】 |
役割 | 企画・運営の共同実施 | 金銭・物品・サービスによる支援 |
責任 | 共同責任 | 主催者の責任 |
権限 | 共同権限(意思決定に関与) | 権限なし(意思決定に関与せず) |
目的 | 共にイベントを成功させること | 主に自社のプロモーション、CSR活動 |
名称表示 | 「〇〇社・△△社 共催」 | 「協賛:〇〇社」など |
リスク | イベント失敗時のリスクを共有 | 主催者のリスクを負わない |
リソース | 人材、資金、ノウハウ、ネットワーク | 主に資金、物品、サービス |
関係性 | 対等なパートナーシップ | 主催者と支援者 |
契約形態 | 共同事業契約、覚書など | 協賛契約書、申込書など |
共催と協賛のメリット
共催のメリット
単独では実現困難な大規模イベントや複雑な企画を、複数の組織が協力することで可能にする点です。具体的には、以下のようなメリットがあります。
- リソースの拡充
人材、資金、ノウハウ、設備など、単独では賄いきれないリソースを共有することで、イベントの規模や質を向上させることができます。 - リスクの分散
イベント開催にはさまざまなリスクが伴います。共催であれば、それらのリスク(経済的リスク、運営上のリスクなど)を分散させることができます。 - ブランドイメージの向上と信用力の強化
複数の組織が共催することで、イベント自体の信用力が増し、参加者からの信頼を得やすくなります。また、共催者のブランドイメージがお互いに良い影響を与え合い、相乗効果で双方の企業イメージ向上に貢献することも期待できます。 - 集客力の向上
各共催者が持つ顧客基盤やネットワークを活用することで、単独開催よりも幅広い層へのアプローチが可能となり、集客力の向上が見込めます。 - 新たな価値創造
異なる視点や専門性を持つ組織が協力することで、単独では思いつかなかったような斬新な企画やアイデアが生まれ、イベントに新たな価値をもたらすことがあります。
協賛のメリット
協賛企業のメリットは、自社の宣伝やイメージアップを図れる点です。主なメリットは以下の通りです。

- ブランディングと認知度向上
イベント会場でのロゴ掲示やブース出展、配布物への掲載などを通じて、多くの参加者に自社のブランドや商品をアピールできます。ターゲット層に直接アプローチできる機会を得られます。 - 企業イメージ向上(CSR活動)
社会貢献活動や地域活性化に貢献している企業としてのイメージを構築できます。特に、NPOや地域イベントへの協賛は、企業の社会的責任(CSR)を果たす姿勢を示すことができます。 - リード獲得と販売促進
イベント参加者に対して直接商品やサービスを紹介したり、アンケートを通じてリードを獲得したりする機会が得られます。イベント限定の割引やサンプリングは、購買意欲を刺激します。 - ネットワーク構築
イベントを通じて、主催者や他の協賛企業、参加者との新たなビジネスチャンスや人脈を構築できる可能性があります。 - ターゲット層へのリーチ
自社の製品やサービスのターゲット層が集まるイベントに協賛することで、効率的に見込み客へアプローチできます。
福岡ソフトバンクホークスへの協賛事例
協賛事例①:ホークスカップ
ホークスカップは、福岡市内の中学生軟式野球チームの頂点を決める大会です。野球というスポーツを通じて子どもたちが心身ともに健全に成長できる環境づくりを推進しています。
本大会へのご協賛は、未来を担う青少年の健全な育成に直接貢献できる社会貢献活動となります。また、大会会場の看板や大型ビジョンへの社名掲出を通じて、地域社会における貴社の認知度を向上させるとともに、積極的な社会貢献活動を広くPRすることが可能です。

協賛事例②:イベント試合への協賛
「鷹祭 SUMMER BOOST」、「ピンクフルデー」、「ファイト!九州」といった注目度の高いイベント試合にご協賛いただくことで、貴社のPRと認知度向上に効率的に貢献できます。
また、これらのイベント試合への協賛は、地域社会の活性化に貢献できるだけでなく、地域住民との新たなネットワーク構築の機会にもつなげられます。

まとめ
この記事では、共催と協賛の違いについて以下の内容を解説しました。
共催と協賛の違い
共催と協賛のそれぞれのメリット
福岡ソフトバンクホークスを通じた協賛の事例
共催と協賛は、イベント成功の鍵となるパートナーシップです。共催は、複数の組織が対等な立場で企画から運営までを共同で行う、深くリスクとリターンを共有する関係です。互いの強みを生かし、単独では難しい大規模な成果を目指します。
一方、協賛は、企業が資金や物品を提供し、イベントを支援する関係です。主催者はイベントの質を高められ、協賛企業はブランディングやプロモーション効果を得ることができます。
どちらの形式を選ぶにしても、綿密な事前準備、そして継続的な信頼関係の構築が、イベントを成功に導くために最も重要です。
『福岡ソフトバンクホークス』では、さまざまな協賛プランを用意しています。詳しくは、こちらをご確認ください。