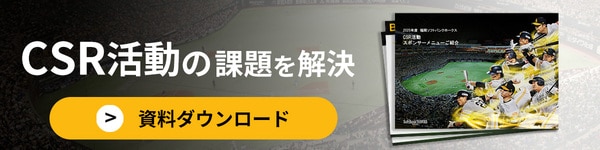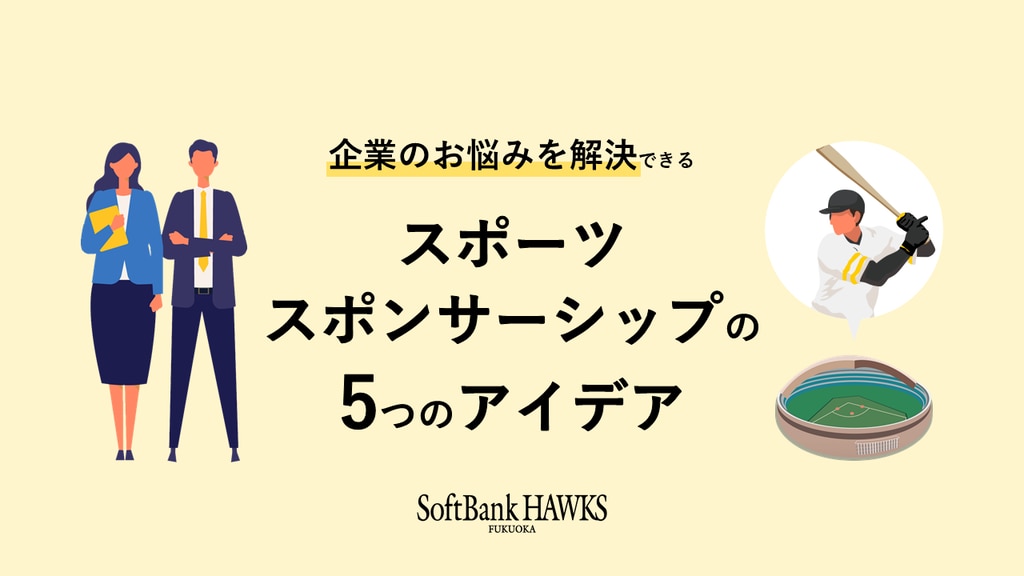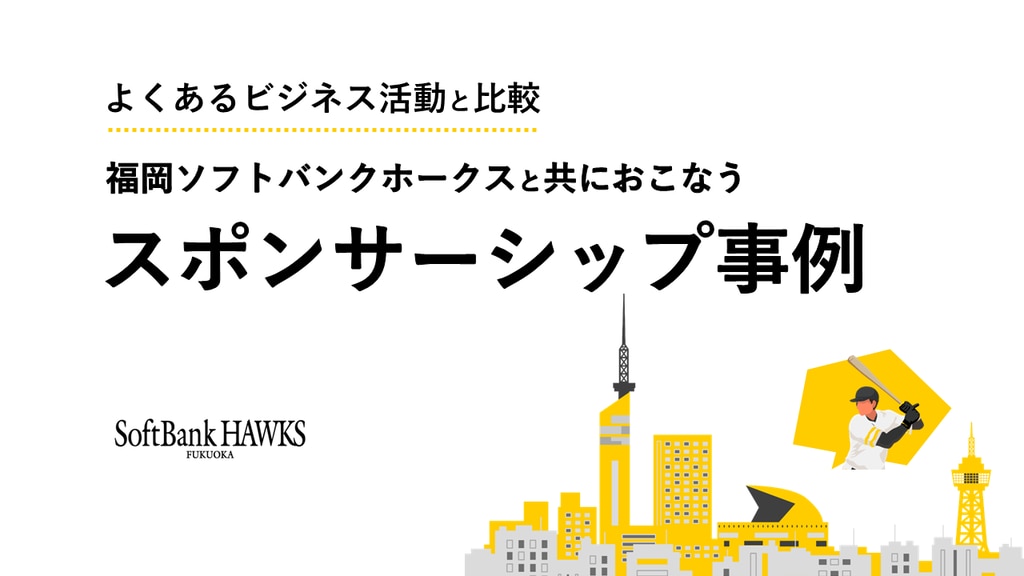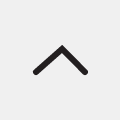CSR活動とは?得られるメリットやホークスのスポンサーシップを活用した事例を解説!

CSR(企業の社会的責任)活動は、企業が社会や環境に与える影響を考慮し、持続可能な発展を目指す取り組みです。近年、CSR活動は単なる慈善活動にとどまらず、企業戦略の一部として位置づけられ注目されています。
この記事では、一般的なCSR活動のご紹介とともにスポンサーシップを活用したCSR活動について解説します。
>おすすめの関連記事はこちら
・企業が社会貢献活動を行うのはなぜ? 取り組む際のポイントとは
目次[非表示]
- 1.CSR活動とは?具体例や原則を解説!
- 1.1.CSR活動とは?
- 1.2.CSR活動が注目される背景
- 1.3.CSR活動の具体例
- 1.4.CSRの7つの原則
- 2.CSR活動と混同しやすい言葉の違いとは?
- 2.1.サステナビリティと違い
- 2.2.SDGsとの違い
- 2.3.CSVとの違い
- 2.4.コンプライアンスとの違い
- 2.5.ボランティア活動との違い
- 3.CSR活動によって生じるデメリット
- 3.1.人件費などのコストの増加
- 3.2.慢性的な人手不足に陥るリスク
- 3.3.業務効率が悪化するリスク
- 4.スポンサーシップを活用したCSR活動で得られるメリット
- 4.1.メリット①「地域コミュニティとの関係構築・活性化」
- 4.2.メリット②「青少年育成」
- 4.3.メリット③「メディア露出」
- 5.CSR活動を行う際の3つの注意点
- 6.ホークスのスポンサーシップを活用したCSR活動の事例
- 7.まとめ
CSR活動とは?具体例や原則を解説!
CSR活動とは?
企業の社会的責任、いわゆるCSR (Corporate Social Responsibility) は、会社が社会に貢献するためのさまざまな活動のことです。
企業は社会の一員として、環境や地域社会が抱える問題の解決に取り組み、より良い未来づくりに役立てることができます。
CSR活動が注目される背景
2000年以降、食品偽装など企業の不正が国内外で繰り返し起きており、大きな社会問題となっています。
また、企業の生産活動による環境への悪影響についても、世界中から厳しい視線が注がれるようになってきました。
こうした状況を受けて、企業が社会からの信頼を得るためには、CSR(企業の社会的責任)を果たすことが、これまで以上に重要になってきています。
CSR活動の具体例
CSR活動には、以下のようなさまざまな取り組みがあります。
▼環境保護
環境に配慮した製品開発やリサイクルプログラムの実施
▼地域貢献
地元コミュニティへの支援やボランティア活動
▼教育支援
学校や教育機関との連携による教育プログラムや奨学金制度の提供
▼健康促進
健康診断やフィットネスプログラムを通じた従業員の健康管理
これらのCSR活動は、社会課題の解決につながるだけでなく、地域住民やお客様など、企業に関わるさまざまな人々からの信頼を得て、企業価値を高めることにもつながる重要な活動となっています。
CSRの7つの原則
CSRについては、国際標準化機構(International Organization for Standardization)が「ISO26000」として国際的な基準を設けています。
企業は、このISO26000に定められた7つの重要な原則に従ってCSR活動を進めることが求められています。
▼CSRに関する7つの原則
-
説明責任
企業活動が社会に与える影響について、十分な説明を行うこと。 -
透明性
経営陣の意思決定や具体的な活動について、社会に対して透明性を保つこと。 -
倫理的な行動
公平さや誠実さなどの倫理観に基づいて企業活動を行うこと。 -
ステークホルダーの利害の尊重
株主だけでなく、債権者、取引先、消費者、従業員など、さまざまな利害関係者に配慮して企業活動を行うこと。 -
法の支配の尊重
自国の法令や、自社に適用される他国の法令を守ること。 -
国際行動規範の尊重
法令だけでなく、国際的に通用している規範を大切にすること。 -
人権の尊重
重要かつ普遍的な人権を守り、尊重すること。
CSR活動は社会課題の解決に寄与するだけでなく、地域住民や顧客などさまざまなステークホルダーから信頼を得られ企業の価値向上にもつながる重要な活動です。
CSR活動と混同しやすい言葉の違いとは?
サステナビリティと違い
サステナビリティ(Sustainability)は「持続可能性」という意味で、環境・経済・社会のバランスを保ちながら、世界を持続可能な状態に保っていこうという考え方です。
これに対してCSRは企業自身の持続的な成長を目指す活動ですが、サステナビリティはより広い視野で環境・経済・社会全体の持続可能性を追求する点で、その意味合いが異なります。
SDGsとの違い
SDGs(Sustainable Development Goals)は「持続可能な開発目標」のことで、2015年に国連で採択された2030年までの世界共通の目標です。
具体的には17の目標と、それらを達成するための169のターゲットが設定されています。
CSRがステークホルダーや社会の期待に応じて企業が自由に活動を選べるのに対し、SDGsは取り組むべき課題があらかじめ定められているという点で異なります。
CSVとの違い
CSV(Creating Shared Value)は「共通価値の創造」という意味で、企業が経済的な価値と社会的な価値の両方を実現できる共通の価値を見出していく考え方です。
一方CSRは、自社の利益を主な目的とせず、社会的課題の解決に取り組むことで企業価値を高めることを目指す点で、CSVとは異なります。
コンプライアンスとの違い
コンプライアンス(compliance)とは、法令や社会的規範を守ることを意味します。このコンプライアンスの強化は、ISO26000が定めるCSRの7つの原則すべてに関わる重要な要素となっています。
しかし、企業がCSRを十分に果たすためには、コンプライアンスを徹底するだけでは足りません。
それに加えて、企業は自社の持つ能力を活かして、社会にどのように貢献できるかを考え、実際に行動に移していくことが必要です。
ボランティア活動との違い
ボランティア活動とは、自分の意思で他人や社会に無償で貢献する活動のことです。企業のCSR活動の中には、従業員による会社周辺の清掃活動のように、ボランティア活動も含まれています。
しかし、CSR活動は必ずしも無償である必要はありません。たとえば、環境・社会・企業統治に積極的に取り組む企業への投資である「ESG投資」は、利益を期待する点でボランティア活動ではありませんが、CSR活動の一つとして考えることができます。
このように、ボランティア活動とCSR活動は、どちらも社会に貢献する取り組みという点では同じですが、ボランティア活動が無償であるのに対し、CSR活動は対価の有無を問わず、企業の幅広い社会貢献活動を指すという違いがあります。
CSR活動によって生じるデメリット
人件費などのコストの増加
CSR活動は人件費などのコストがかかるにもかかわらず、すぐに目に見える形での業績向上につながるとは限りません。
そのため、企業がCSR活動を継続的に行っていくためには、長期的な視点と粘り強い取り組みが必要となります。
慢性的な人手不足に陥るリスク
CSRを意識して企業活動を行うことで、通常業務に加えて新たな作業が発生し、時には本来の仕事とあまり関係のない活動も必要になってきます。
本業とCSR活動の両方を高い水準で実施するためには、十分な人員を配置する必要があります。
しかし、コストの問題などですぐに人員を増やせない場合、慢性的な人手不足に陥ってしまう可能性があります。
業務効率が悪化するリスク
企業が売上や業績の向上だけに注力した方が、CSRを意識して活動するよりも業務効率は上がりやすいと言えます。
つまり、CSR活動には多かれ少なかれ、業務効率を犠牲にする側面があります。このようなCSR活動による業務効率の低下は、社会からの信頼を得るための将来への投資として考える必要があります。
スポンサーシップを活用したCSR活動で得られるメリット
CSR活動として、地域のスポーツイベントやスポーツチームへのスポンサーシップも効果的な取り組みの一つです。
このような支援活動は、地域の活性化につながるだけでなく、メディアでの露出機会も増やすことができ、企業価値の向上にもつながる有効な方法です。
メリット①「地域コミュニティとの関係構築・活性化」
地域スポーツイベントへの支援には、地域住民を巻き込みコミュニティの結束を強める効果があります。地域住民との関係性が深まり、長期的に良好な信頼関係が築かれます。 また企業が地域スポーツを支援することで、その地域全体の活性化やイベントの集客数が増加し、その結果として地域経済への好影響が期待できます。
▼幼稚園・保育園向けの野球教室の様子

メリット②「青少年育成」
スポーツは青少年にとって重要な教育的要素を含んでいます。企業がスポンサーとなることで、子どもたちに運動する機会を提供し、健全な成長を促進します。
▼ホークス選手から野球指導を受けられるイベント(ベースボールキッズ)

メリット③「メディア露出」
スポーツイベントへの関与は世間からの注目度が高くテレビをはじめとした、さまざまなメディアでの露出が期待できます。結果として企業の価値向上や認知度向上につながります。
▼ホークス選手から野球指導を受けられるイベント(ベースボールキッズ)

CSR活動を行う際の3つの注意点
企業がCSR活動を進めていく上で、以下のような点に気を付けて取り組むことが大切です。
①自社の得意分野を活かしてCSR活動を行う
CSR活動には幅広い取り組み方がありますが、効果的に活動を進めるためには、自社の得意分野を活かすことが重要です。
そのため、社会が必要としていることと、自社の持つ能力や経験を照らし合わせながら、具体的にどのようなCSR活動に取り組むべきかを慎重に検討し、選んでいく必要があります。
②コストとリターンを分析した上で無理なく行う
CSR活動は単なる慈善事業ではなく、会社が中長期的に利益(リターン)を得るために行う活動です。
そのため、CSR活動にかかる費用と、それによって得られる目に見える・見えないリターンを比較検討した上で、自社に利益をもたらすことができる方法で取り組むことが大切です。
③外部に依頼することも検討する
CSR活動を既存の従業員に任せると、通常の業務を含めた仕事が過密になってしまう可能性があります。
そのため、できれば専門部署を設けてCSR活動を担当させ、他の部門の本来の仕事に支障が出ないような体制を整えることが望ましいでしょう。
もし社内で専門部署を設置することが難しい場合は、弁護士、公認会計士、税理士といった専門家に協力を依頼し、CSR活動の一部を担当してもらうといった方法も検討できます。
ホークスのスポンサーシップを活用したCSR活動の事例
既に多くの企業が取り組んでいるホークスのスポンサーシップを活用した地域貢献活動の事例をご紹介します。
なお、社会貢献活動を行う際のポイントは、こちらをご確認ください。
ホークスカップへの協賛
NPO法人ホークスジュニアアカデミーでは、九州・沖縄・山口地区の6つの中学硬式野球クラブがリーグの垣根を越えて交流し、同地区のNo.1を決定する大会としてホークスカップを開催しています。ホークスカップへの協賛を通じて、中学野球の発展と野球を通じた青少年の健全育成に寄与することができます。
また、みずほPayPayドームで行われる準決勝・決勝では協賛企業様の社名をドームのビジョンに掲出いたします。ビジョンへの社名掲出を通じて、企業の社会的責任を示す良い機会となります。
▼ホークスカップの様子

▼ホークスカップ開催時のビジョン映像
▼ホークスカップ開催時のマウンド

王貞治ベースボールミュージアム オフィシャルスポンサー
BOSS E・ZO FUKUOKAの4階にある王貞治ベースボールミュージアム は、野球人・王貞治の魅力を核としてその魅力の根源に迫り、次世代へと継承しようとする未来志向のスポーツミュージアムです。王貞治の球史を振り返る展示品や打つ・投げる・捕るなど体験型アトラクションをお楽しみいただけます。
王貞治ベースボールミュージアムのオフィシャルスポンサーになることで、当時を知らない世代にも野球人・王貞治の波乱万丈の道のりや試合映像を最新の展示手法で学ぶ機会を提供することができます。
また、オフィシャルスポンサーの企業様の社名を本施設やみずほPayPayドームのビジョンなどで掲出いたします。王貞治ベースボールミュージアム やホークス公式戦に子供たちを招待することで、子供たちが未来に向けて夢を見つけるきっかけづくりに寄与し、企業の社会的責任を示すこともできます。
▼王貞治ベースボールミュージアム

▼ホークス公式戦でのオフィシャルスポンサーの紹介

なお、地域貢献につながるメセナ活動については、こちらの記事をご確認ください。
まとめ
この記事では、CSR活動について以下の内容を解説しました。
- CSR活動とは?具体例や原則を解説!
- CSR活動と混同しやすい言葉の違いとは?
- CSR活動によって生じるデメリット
- スポンサーシップを活用したCSR活動で得られるメリット
- CSR活動を行う際の3つの注意点
- ホークスのスポンサーシップを活用したCSR活動の事例
CSR活動は企業戦略としてますます重要性を増しており、その一環としてスポンサーシップを活用した地域スポーツ振興も注目されています。企業が社会課題解決に取り組むことで、自社の価値向上だけでなく、地域社会全体にも良い影響を与えることができます。今後もこのような取り組みが広がることが期待されます。
『福岡ソフトバンクホークス』では、野球チームを応援するスポンサー企業を募集しています。スポンサー企業さまに向けて、多様なCSR活動のメニューを用意しています。貴社のCSR活動や、ブランディングなどにご活用ください。